公認会計士は、会計のスペシャリストとして高い社会的信頼を得ており、高収入も期待できる専門職です。主に監査やコンサルティングなど、さまざまな業務に携わっていますが、具体的にどのような仕事をしているのでしょうか?
本記事では、公認会計士の仕事内容や年収、働き方の特徴、税理士との違いまで、初めての方にもわかりやすく解説します。
公認会計士の仕事とは?代表的な業務をわかりやすく解説

公認会計士の主な仕事は、法定独占業務である監査(会計監査、内部統制監査)など、主に以下のような業務をおこなっています。
税務業務+中小企業コンサルティングとは?
会計士の独立後の進路として最も多いのが、税理士登録を行い、中小企業の税務顧問とコンサルティングを兼ねるスタイルです。
会計士は監査法人や企業での実務経験を通じて、決算書の読み解き・資金繰りの改善・補助金申請支援など、財務面での高い専門性を持っています。
そのため、税務申告だけでなく、経営全体を俯瞰したアドバイスが可能です。
また、税理士資格者のみの事務所との差別化として、「財務に強い会計士」というブランディングで成功している事務所も少なくありません。
中小企業の“かかりつけ医”のような立場で、経営者に寄り添った支援が求められています。
会計監査とは?企業の財務諸表を社外からチェックする業務
会計監査は、公認会計士の代表的な業務のひとつで、企業の財務諸表が正しく作成されているかを第三者としてチェックする仕事です。
監査法人に所属する会計士が担当することが一般的で、上場企業や大企業が主な対象となります。
独立後に監査業務を継続する会計士は比較的少なく、多くは税務やコンサルに軸足を移します。
内部統制監査とは?企業内部のルールと運用状況を評価する業務
内部統制監査とは、企業内の業務ルールや運用体制が適切に整備され、運用されているかを評価する業務です。
これは主に上場企業や大企業を対象に行われ、監査法人に所属する会計士が実施するケースが多くなっています。
独立開業後の業務としてはあまり一般的ではなく、企業勤め時代の経験として活かされることが多いです。
税務業務はできる?公認会計士と税理士の関係と違い
公認会計士は、税理士登録により税務業務をおこなうことができます。
公認会計士が税理士登録するためには、一定の税法に関する研修を修了し、考査に合格後、税理士会へ登録する必要があります。
ただし2017年3月31日までに公認会計士試験に合格した方は、一部の要件が免除されます。
中小企業向けコンサルティング業務とは?資金繰り・経営改善をサポート
公認会計士が提供するコンサルティング業務は、中小企業を対象とした経営支援にシフトしています。
資金繰りの改善、事業再生、補助金申請、財務分析など、経営者の右腕として伴走する形が主流です。
特に、税務顧問とセットでの支援を行う会計士が多く、単なるアドバイスにとどまらず、実務にも踏み込んだ支援が評価されています。
会計士の専門性を活かし、数字に裏打ちされた提案ができる点が強みです。
財務アドバイザリー(M&A・企業再生など)
M&Aにおける事業価値評価や財務デューデリジェンスなどです。また経営状態が悪化した企業の再生を支援する業務などがあります。
IPO支援(上場準備・内部統制)
IPO(新規株式公開)を予定している企業を対象に、上場準備をアドバイスする業務です。財務諸表の適正化、上場基準との適合確認、内部統制の強化などを支援します。
経営戦略コンサルティング(成長支援)
経営戦略などに関するコンサルティング業務です。新規事業開発、M&A、組織再編など幅広く、得意分野をもって活躍する人が多く見られます。
内部統制コンサルティング(CSR・報告書の信頼性保証)
企業のCSR(企業の社会的責任)や内部統制に関する助言をおこないます。内部統制の整備・運用・評価・対策などのアドバイス、内部統制報告書の作成支援などを支援します。
公認会計士が関わる相手・業務内容の実例とは?

公認会計士は、上場企業を対象とした監査だけでなく、独立後には中小企業を相手に税務や経営支援を行うケースが主流です。
ここでは、実際に会計士が関わる顧客と業務内容の実例をご紹介します。
中小企業の税務・経営支援が主力に|独立会計士の実務とは?
独立開業した公認会計士の多くは、税理士登録を行い、中小企業の税務顧問や財務コンサルティング業務を中心に活動しています。
資金繰り改善、補助金申請、経営計画の策定、事業承継支援など、経営の実務に直結した支援が求められています。
特に、監査法人での経験や財務知識を活かした「数字に基づいた改善提案」は、税理士事務所との差別化にもつながっています。
中小企業の経営者にとって、会計士は単なる税務処理担当ではなく、「信頼できるパートナー」として位置づけられる存在です。
学校法人の監査は個人事務所が多い|約7割が個人事務所
一方で、学校法人の監査においては個人事務所が主力となっています。これは、上場企業のように大規模な開示義務がないことなどが背景にあります。
上記の金融庁のレポートによると、学校法人の監査社数4,889社のうち、個人事務所が3,352社(68.6%)を占めます。
このように、中堅・中小規模の法人に対しては、個人事務所や中小規模の監査事務所が多く関わっており、独立後の会計士にとっても一つの業務領域となっています。
公認会計士の仕事はきつい?年収や労働時間をデータで解説

「公認会計士の仕事はきつい」と耳にすることがありますが、その実態はどうなのでしょうか?
本章では、公認会計士の労働時間や年収、独立後の収入まで、信頼性の高いデータをもとにわかりやすく解説します。
「激務」と言われる理由とは?忙しい時期や求められる知識量
公認会計士は激務と言われる主な理由は以下のとおりです。
- 繁忙期がある
4月から6月に業務が集中します。企業の決算が3月に集中するためです。 - 効率的な作業を求められる
監査報酬は、タイムチャージ方式(監査作業時間×時間あたり単価)により決定されることが一般的であり、効率的な作業を求められます。 - 合格後も勉強が必要
公認会計士合格に必要な勉強時間は3,000時間から5,000時間と言われています。合格後も研修受講が義務づけられており、年20単位以上、3年間で120単位以上の受講が必要です。さらに会計基準の改正など知識のアップデートが求められます。
平均業務時間はどれくらい?大手と準大手で比較
金融庁のレポートによると、年平均業務時間は大手監査法人勤務の場合2,039時間、準大手監査法人勤務の場合1,601.4時間です。
平均年収はいくら?最新統計データから読み解く
2024年賃金構造基本統計調査から推計すると、監査法人などに勤務する公認会計士(税理士を含む)の平均年収は約856万円です。(決まって支給する給与額55.77万円×12か月と年間賞与など187.02万円の合計)
※この統計は「公認会計士・税理士」を含むカテゴリであるため、厳密には職域ごとの差異がある点にご留意ください。
独立開業した場合の売上は?事務所の平均収入とは
独立開業後は自らの努力で収入を増やせる可能性があります。公認会計士事務所の売上高は従業者数によって異なり、1人あたり平均売上高は1,750万円です。
| 従業者数 | 事業所あたり売上高 | 1名あたり売上高 |
|---|---|---|
| 全体平均 | 2億832万円 | 1,750万円 |
| 1名から4名 | 2,188万円 | 1,046万円 |
| 5名から9名 | 6,471万円 | 1,002万円 |
| 10名から19名 | 1億4,486万円 | 1,103万円 |
【参考】2024年賃金構造基本統計調査|e-Statより、一般労働者の第5表
【参考】2021年経済センサス活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 売上(収入)金額等|e-Statより、表番号7-1
※売上高には経費が含まれているため、「収入=利益」ではありません。実際の年収はここから人件費や事務所運営費などを差し引いた額になります。
公認会計士の働き方|監査法人勤務・組織内会計士・独立開業まで

公認会計士の多くは監査法人に就職してキャリアをスタートさせますが、その後は企業勤務や独立開業など、さまざまな道に進むことが可能です。本章では、それぞれの働き方の実態と割合をデータに基づいて解説します。
監査法人勤務の割合は?約40%が所属
公認会計士登録者数35,532名のうち、14,427名(40.6%)が監査法人に所属しています。このうち10,516名が大手監査法人の所属です。(2024年3月末時点)
新卒や会計士試験合格後すぐに監査法人に就職する人が多く、キャリアの第一歩として主流の選択肢です。
組織内会計士とは?企業や官公庁での活躍事例
組織内会計士とは、一般企業や官公庁に勤務する公認会計士のことです。
たとえば、上場企業での経理部門や、官公庁での財務管理業務などに従事するケースがあります。
日本公認会計士協会の組織内会計士ネットワークで見ると、正会員数は2,496名(上場企業1,219名、非上場企業1,005名など)です。(2024年12月末時点)
独立開業の実態は?割合・メリット・働き方の自由度
厚生労働省の「job tag」で見ると、自営・フリーランスの公認会計士の割合は23.4%です。
独立開業は、自ら思い描くワーク・ライフバランスを実現できる可能性がある、地方においても需要がある、税理士事務所としてキャリアの幅を広げることができるなどの魅力があり、公認会計士の主なキャリアの1つとなっています。
ただし、顧客開拓や収入の不安定さなど、ビジネス面での自己管理も求められる点には注意が必要です。
公認会計士は監査以外できない?同時提供禁止ルールをわかりやすく解説

公認会計士は、企業の財務諸表をチェックする「監査」だけでなく、税務や会計コンサルティングなど多様な業務にも対応できます。ただし、同一のクライアントに対して監査と非監査業務を同時に提供することは原則禁止されています。
本章では、その理由や具体的な制限内容について、わかりやすく解説します。
「1項業務」「2項業務」とは?法的な区分と具体例
公認会計士の業務は、公認会計士法第2条に「1項業務」「2項業務」として定められています。
- 1項業務
企業の財務諸表について、監査や証明を行う業務です。監査報告書の作成などが該当します。
- 2項業務
公認会計士の資格を使って、財務書類の作成や、会計に関する調査・助言を行う業務です。
監査と税務の同時提供が禁止されている理由
公認会計士は、同一のクライアントに対する監査と税務の同時提供が禁止されています。監査法人の場合、従業員のうち1名でも税務業務をおこなっているクライアントに関して、すべての監査が禁止されます。
税務業務はクライアントの立場にたって、税務書類の作成などをおこなう仕事です。税務をおこなっているクライアントへの監査は“自己監査”となり、監査の独立性を保つことが難しくなってしまいます。
監査と非監査業務の同時提供に関する具体的な制限内容
公認会計士法上の大会社などについては、1項業務と一定の2項業務の同時提供についても禁止されています。
具体的には、財務諸表の作成など以下の業務をおこなっている企業に対して、監査が禁止されます。監査の独立性を確保することが目的です。
公認会計士の仕事に関するよくある質問(FAQ)
公認会計士の仕事に関するよくある質問は以下のとおりです。
Q1:公認会計士と税理士の違いは?
A.公認会計士と税理士は、法律で定められた独占業務が違います。一言で表すと「公認会計士は監査の専門家、税理士は税務の専門家」です。実務上は、公認会計士が税理士登録を行って税務も行うケースがあり、両者の業務が重なる部分も存在します。
Q2: 公認会計士の主な勤務先はどこ?
A.公認会計士の約4割が監査法人に所属しています。そのほか、独立開業や一般企業の組織内会計士などが多く見られます。
Q3: 公認会計士の仕事はAIに奪われる?
A. 一部の定型業務はAIによって効率化される可能性はありますが、完全に仕事がなくなるわけではありません。監査計画やリスク評価、表情や態度の変化への気づきなど、人間にしかできない部分も多くあります。
Q4: 監査以外の仕事もできる?
A.できます。たとえば、企業再生コンサルティングやIPO支援、経営企画部門などでの活躍が期待されています。ただし監査業務を主とする公認会計士がそのほかのスキルを身につけるためには、コンサル部門への移籍、独立開業などキャリアチェンジが必要です。
Q5:独立開業する公認会計士が多いのはなぜ?
A.主な理由は次のとおりです。
- 自らの努力で収入を増やしたい
- ワーク・ライフバランスを重視したい
- 地方で仕事をしたい
- 監査以外のサービスに力をいれたい
経営革新等支援機関推進協議会の活用で、独立後の不安を解消
独立を考えている会計士や事務所の差別化について悩みごとがある事務所は、経営革新等支援機関推進協議会をご活用ください。
本協議会は全国約1,700事務所が参加し、事務所の開設・収益化・差別化をサポートするノウハウとサービスを月額30,000円(税別)で利用できます。
監査法人からの独立を支援する充実のサポート体制
会計事務所を独立開業するときは、顧客とスタッフの確保が必要です。
本協議会は、販促ツールの提供、スタッフ採用に関する求人関連個別相談、求人媒体のご紹介などスムーズな開業をサポートしています。
税務未経験者向け研修やツールが充実
公認会計士の独立後は、税務が中心の事務所となることが多いと言われています。
本協議会は、細かなノウハウが求められる税務実務を身につける動画研修など、税務未経験者をサポートする豊富なツールを利用できます。
月額3万円で使える主なサービス一覧(F+prus、ACADEMYなど)
本協議会は月額会費の範囲内で、会計事務所の収益化をトータルでサポートする以下のサービスを利用できます。
- 中小企業経営者がわかりやすい財務分析・提案ツール『F+prus』(エフプラス)
- 座学から実務までを学べる税理士事務所の監査担当者向け動画研修プログラム『ACADEMY』
- 事務所名を入れるだけ!すぐに活用できる販促ツールの提供
まとめ|公認会計士の仕事の実態と、キャリアの可能性とは
公認会計士の深い会計知識は、多くの一般企業から求められます。またシステム構築や内部統制など経営管理ノウハウについてもニーズが強く、活躍するフィールドは幅広いと言えます。
しかし公認会計士は監査業務と非監査業務の同時提供禁止ルールがあります。多くの企業からのさまざまな期待に応えるためには、独立開業が有力な選択肢となります。
独立開業に不安がある方は、まずはお気軽に経営革新等支援機関推進協議会へご相談ください。
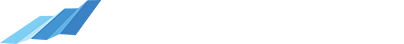
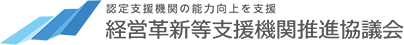
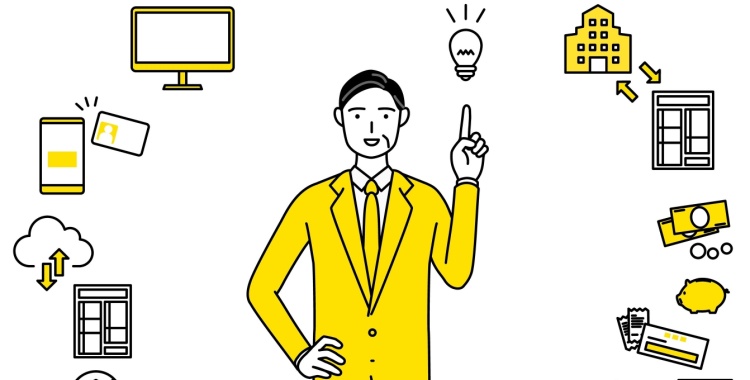








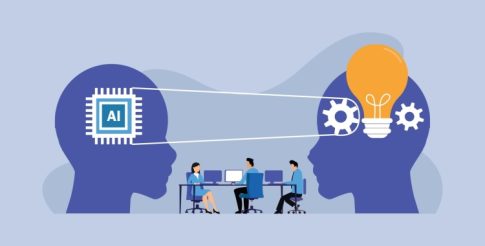



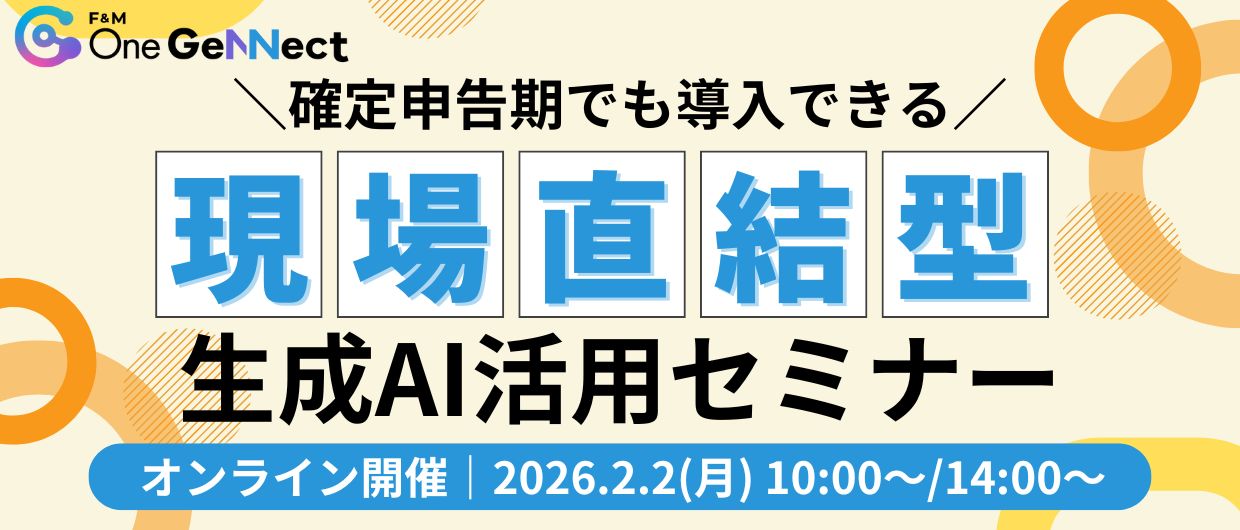
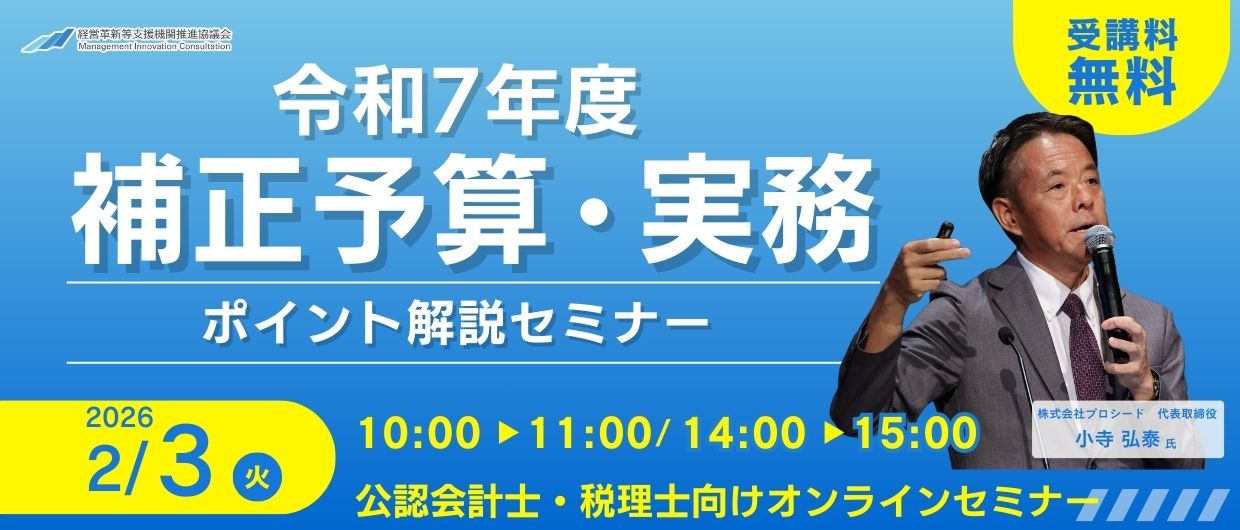
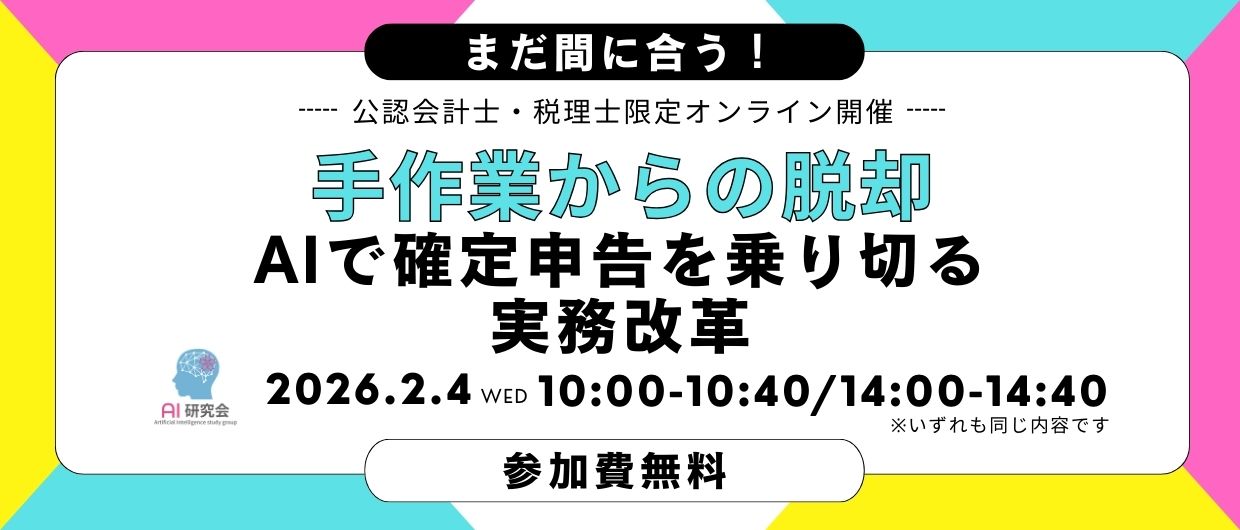


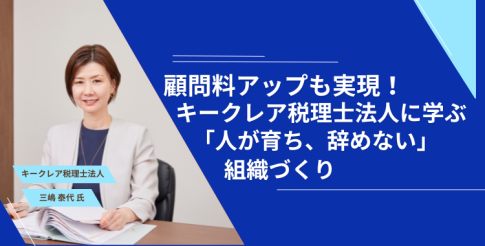



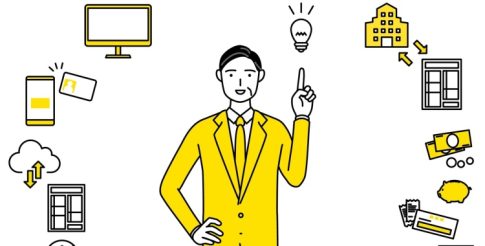




【引用】大会社等監査における非監査証明業務について|日本公認会計士協会