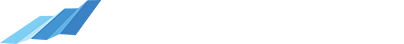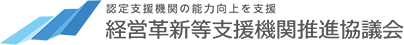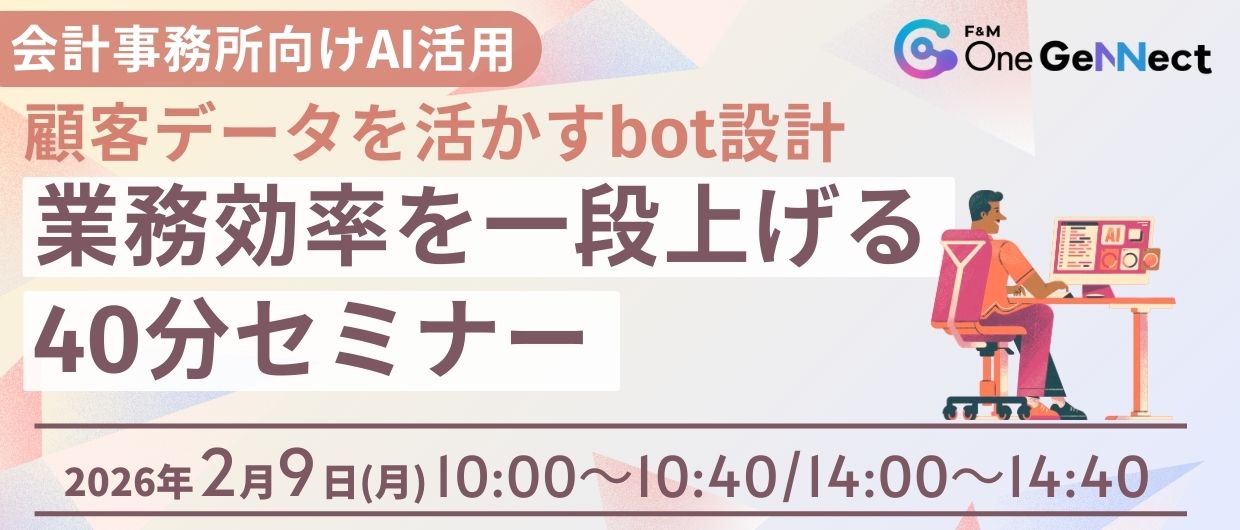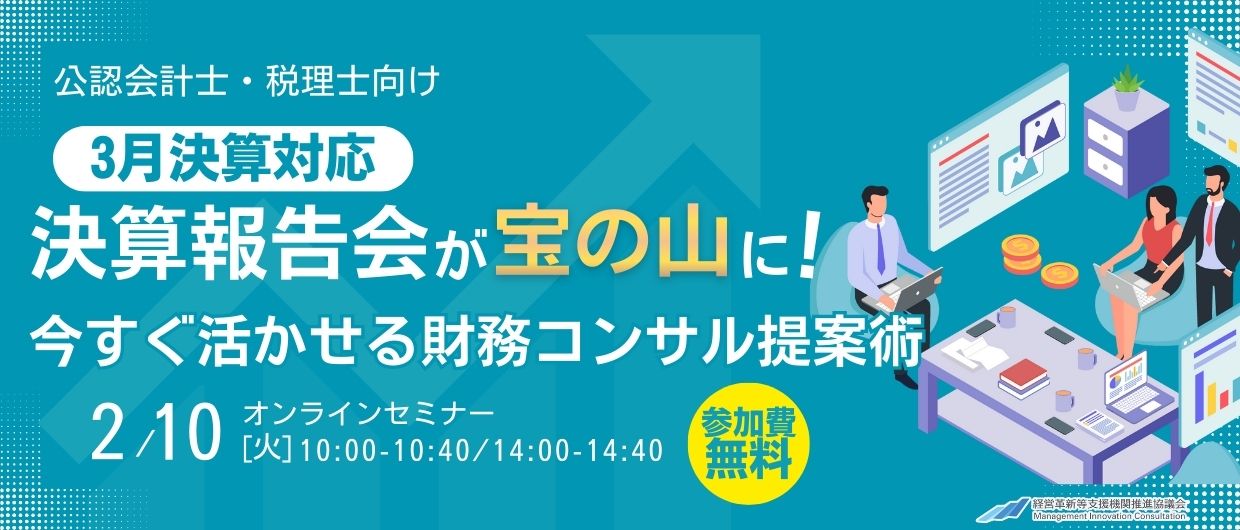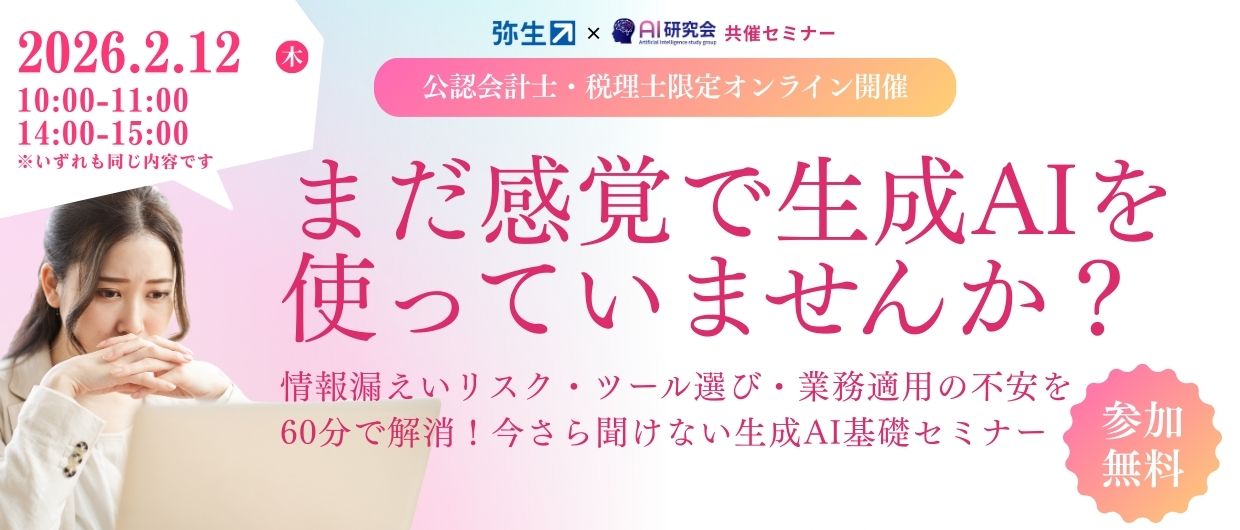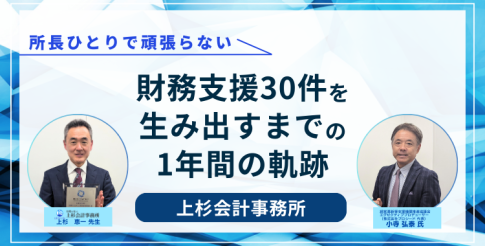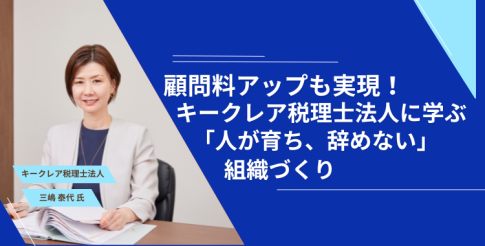2025年6月に行政書士法が改正され、2026年1月から施行されます。
今回の改正で注目されているのは、従来は法解釈により運用されてきた「有償でおこなう補助金申請書の作成・提出は行政書士の独占業務」であることが、条文上でより明確化された点です。
本記事では、行政書士法改正のポイントと、2026年以降に税理士などが顧問先の補助金申請を支援する際の注意点について解説します。

2025年行政書士法の主な改正点【2026年1月施行】
2025年6月に改正された行政書士法(以下、単に「法」といいます)が、2026年1月1日から施行されます。主な改正点は次の2つです。
業務の制限規定の趣旨の明確化
行政書士または行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加わりました。
補助金申請書の作成の対価が、例えば会費やコンサルティング料などであっても、「報酬」に該当することが明確となりました。(法第19条)
両罰規定の整備
無資格者が行政書士の独占業務をおこなうなどの違反があった場合、違反者だけでなく、所属する法人に対しても罰金刑などが科されることとなりました(法第21条の2ほか)
【参考】【会長談話】「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について|日本行政書士連合会
行政書士法改正で2026年から補助金申請は行政書士の独占業務?
2025年の行政書士法改正により、従来は総務省の「見解」として示されていた『他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」など、どのような名目であっても、対価を受領して、業として官公署に提出する書類を作成することは違法』という内容が、条文に明記されました。
ただし、補助金申請に関する「助言」や「支援」は行政書士でなくとも可能です。
上記を大きくまとめると次のとおりです。
官公署提出書類の「作成」「提出」の場合|行政書士の法定独占業務
官公署へ提出する書類の作成と提出は、行政書士の独占業務とされています。(法第1条の3)
「有償」「業として」おこなう場合|行政書士の独占業務と明記(2025年改正)
行政書士でない者は、行政書士の独占業務である官公署へ提出する書類の作成を、有償で、業としておこなうことができません。(法第19条)
「有償」とは、その対価の名目を問わないことが明文化されました。「業として」とは、反復継続性と事業遂行性がある行為を指しています。
一回限りであっても、何らかの対価を得て、事業としておこなう場合は行政書士の業務であると判断されるといえます。
「助言」「支援」のみの場合|「相談」の範疇であれば行政書士資格は不要
補助金の申請書を企業が作成する企業へ作成上の注意事項を説明するなど、「助言」や「支援」をおこなうことは行政書士の独占業務ではありません。
総務省は2022年に「グレーゾーン解消制度」における回答として、『相談の範疇である限りにおいて、行政書士の独占業務とされている書類の作成には当たらない』との解釈を示しています。
この解釈における「相談」とは、一般的な改善案や経験則、補助金の公募要領などに基づいて改善案を提示することを指すとしています。例として、『この部分についてもっと明確に記載』『この部分について論点を絞った内容を作成』などがあげられています。
違反時の罰則|非行政書士の違反行為は罰則あり
行政書士法に違反した場合は罰則があり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。
【引用】行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)(2025年6月13日)|総務省
【参考】新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表(2022年2月16日)|総務省
行政書士法改正で税理士がおこなう対策とは?
2026年1月1日から改正行政書士法が施行されることにあわせて、税理士事務所がおこなっておきたい主な対策は次のとおりです。
スタッフのコンプライアンス意識を高める
事務所スタッフがおこなうサービスが違法行為とならないよう、所内研修などでコンプライアンス意識を高めておく必要があります。
顧問先から「忙しいから代わりに作成しておいてほしい」と依頼され、厚意で代行した行為が法律違反となる可能性もあるためです。
繁忙な事務所における研修には、税理士事務所向けの動画研修を活用することも有効です。
ほかの士業事務所との連携を強化する
行政書士や中小企業診断士、社会保険労務士などほかの士業との連携を深めることも有効です。
ほかの士業と連携することで顧問先に幅広い専門サービスを提供でき、顧客満足度の向上につながります。
行政書士登録を検討する
税理士は行政書士試験を受験せずに行政書士として登録することが可能です。
補助金申請書の作成代行などに取り組む場合は、税理士と行政書士のダブルライセンスを検討できます。
税理士は行政書士になれる?ダブルライセンスのメリット・デメリットとは?
税理士が行政書士として登録することで、より幅広いサービスを顧問先へワンストップで提供できます。例として、創業相談と同時に会社設立や許認可申請をおこなう、相続税の相談から遺産分割協議書を作成するなどがあげられます。
税理士が行政書士として登録する際の主なメリット・デメリットは次のとおりです。
メリット①:税理士は行政書士として登録可能
税理士、または税理士となる資格を有する者は、行政書士試験を受験せず行政書士として登録できます。なお税理士としての登録の有無は問われません。
メリット②:サービスの拡充、収入の増加
税理士が行政書士として登録することで、会社設立や相続など顧問先支援業務を拡大でき、新規顧客獲得や事務所収入の増加につながります。
メリット③:顧問先の満足度向上
創業(起業)予定者の税務相談から会社設立時の許認可申請など顧問先支援業務をワンストップで提供でき、顧客満足度を高めることができます。
デメリット①:登録事務、登録コスト
行政書士業務をおこなうためには行政書士会への登録が必要です。行政書士会に登録する費用、年会費などのコストが発生します。
具体的な金額については所属する行政書士会によって異なります。初期費用の目安は約30万円といわれています。
デメリット②:税理士事務所内で行政書士事務所を開設できない
税理士事務所と別に、行政書士事務所を開設する必要があります。

改正行政書士法に関するよくある質問(FAQ)
2026年1月施行の改正行政書士法に関するよくある質問とその回答は次の通りです。
Q1:2025年の行政書士法改正(2026年1月施行)の影響とは?
A.主な影響として次の2つがあげられています。
- 補助金申請書類の作成は、企業が行政書士へ依頼またはそのほかの専門家の支援を受けて自ら作成する原則が浸透する
- 許認可申請から行政不服申立てまで特定行政書士がワンストップで対応できる
Q2:行政書士法の改正で補助金申請に影響は出る?
A.行政書士資格がない者による申請代行や“闇コンサル”に対するけん制効果が期待されています。
Q3:行政書士法の改正で補助金申請は行政書士の独占業務となった?
A.行政書士の独占業務となる行為の例は次のとおりです。
- 補助金申請書や計画書などを業として有償で作成する
- 補助金申請書の作成を実質的に代行する
- 申請者に代わり、官公署へ申請書を提出する
Q4:補助金申請書類の作成相談・添削は行政書士しかできない?
A.総務省の見解によると、『一般的な改善案や経験則、補助金の公募要領などに基づいた改善案を提示する』などの指導・助言は相談に該当し、行政書士以外の者ができるとされています。
Q5:補助金申請における「相談」と「作成」との違いとは?
A.作成とは、申請書をまるごと作成することです。相談とは、『依頼者の趣旨に沿って、どのような書類を作成するか、書類にはどのような事項を記入するかなどについて、質問に対し答弁し、指示し、または意見を表明するなどの行為』であると総務省が見解を示しています。
税理士の業務拡充は経営革新等支援機関推進協議会が一気通貫にサポート
2026年以降の補助金申請は、企業が専門家と相談しながら主体的に作成することが原則であることが明確になるといわれています。
このため、申請書の作成に不慣れな企業が、税理士や中小企業診断士など専門的な資格をもつ支援機関へ相談するケースが増える可能性があります。
税理士は中小企業経営者にとって最も身近な相談相手です。税理士は顧問先に対して、補助金など公的支援策の紹介・事業計画書などのフォーマットの提供・顧問先が作成した計画案に対するコメント・締め切りの注意喚起など、顧問先がおこなう申請に寄り添った支援が引き続き必要です。
顧問先へ案内する公的支援策のチラシや計画書のフォーマットの提供、顧問先の申請についてのアドバイスなどは、全国約1,700事務所が参加する「経営革新等支援機関推進協議会」が一気通貫でサポートします。
同協議会は、事務所スタッフの採用・教育支援、財務コンサルティング、補助金・優遇税制支援を顧問先に提供できるよう、研修会や各種フォーマットを通じてノウハウと仕組みを提供しています。利用料は月額3万円(税別)です。
まとめ
2025年に行政書士法が改正され、2026年1月1日から施行されます。本改正によって、補助金申請書など官公署へ提出する書類を、業として、有償で作成する行為は行政書士の業務であることが、法の条文に記載されました。
行政書士資格をもたずに補助金申請書類の作成を代行する者へのけん制効果が期待されるとともに、企業が信頼できる専門家と相談しながら作成する原則が徹底されるといわれています。
税理士は中小企業の経営者にとって最も身近な専門家であり、作成に不慣れな経営者の申請書作成を支援するニーズが高まる可能性があります。
顧問先支援サービスの拡充に悩みごとがある会計事務所様は、経営革新等支援機関推進協議会へお気軽にご相談ください。