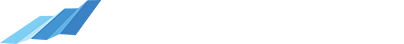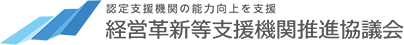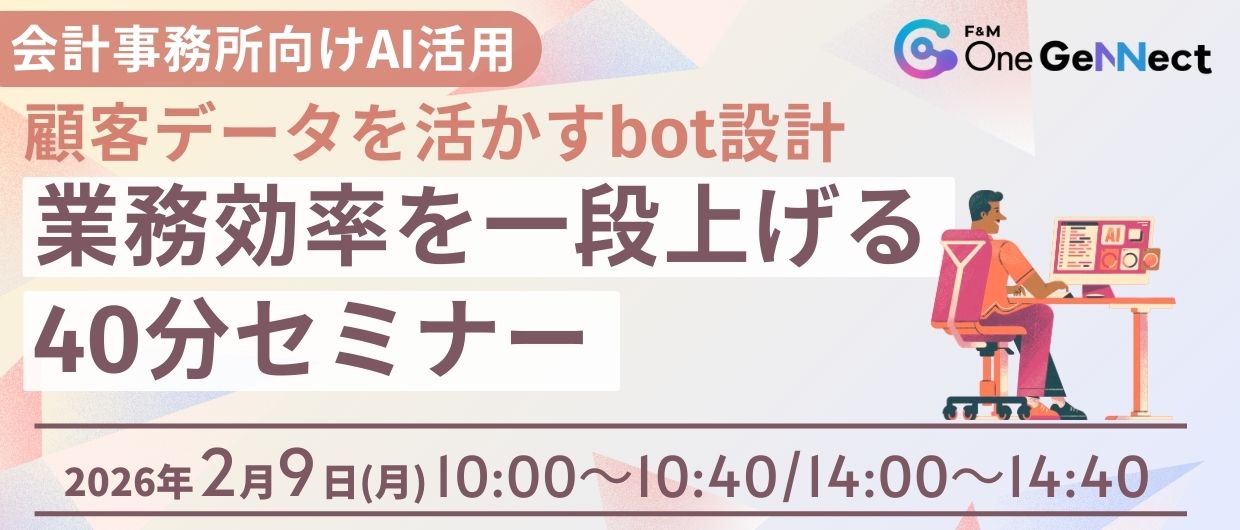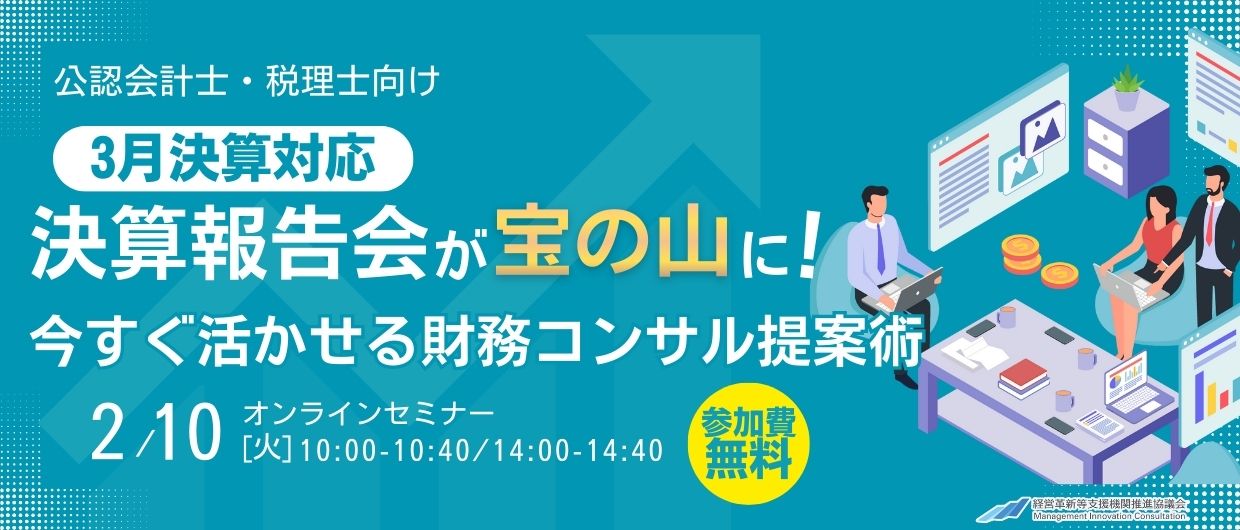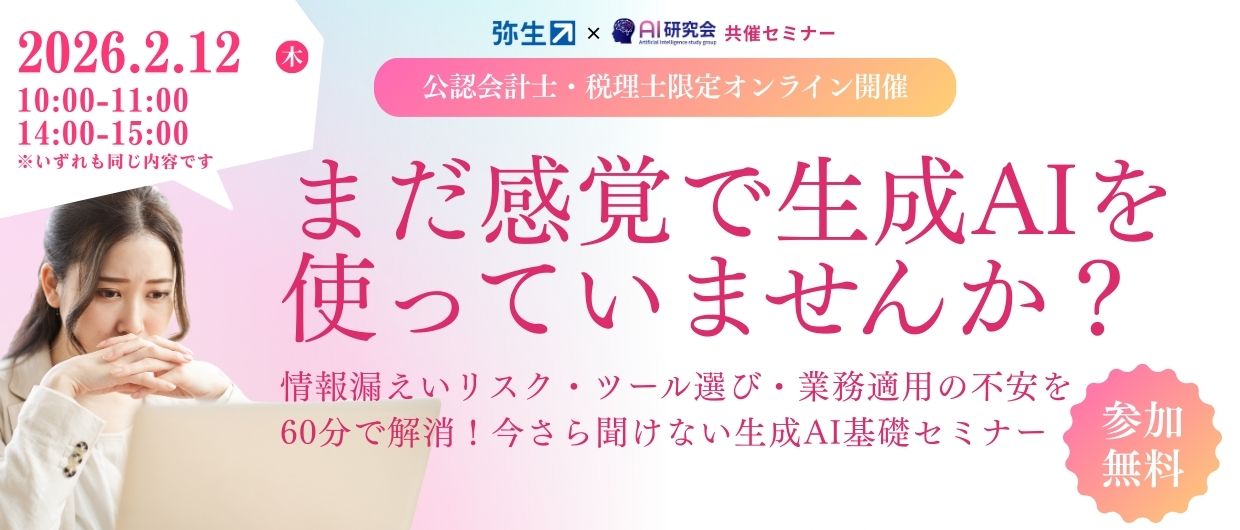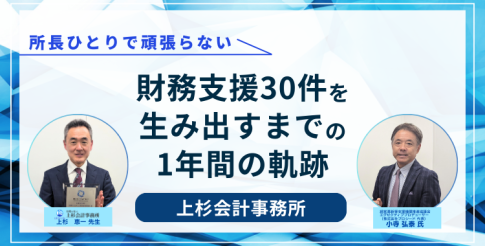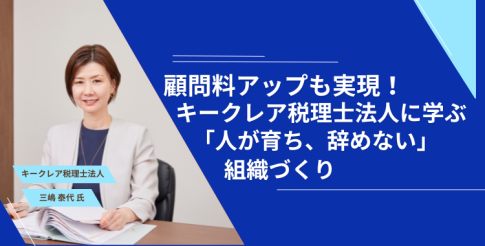公認会計士は監査を独占業務としており、独立開業に向いた資格です。中には資格取得後にいきなり独立開業する人もいます。
本記事では、公認会計士はいきなり独立できるか、独立開業後に多いといわれている税務中心の事務所として成功するためのポイントについて解説します。
公認会計士としていきなり独立できる?

公認会計士は試験合格後、3年間以上の実務経験と実務補習の修了をもって公認会計士の資格を取得します。
公認会計士の資格を取得した後については特に制限がなく、資格取得後、すぐに独立するこが可能です。
公認会計士が独立する年齢
公認会計士が独立する年齢をまとめた公的な資料はありませんが、5年間から10年間ほど経験した後に独立することが多いといわれています。
金融庁が発表している「合格者調」によると、2024年公認会計士試験合格者の年齢は「20歳から24歳」が61.5%と最多です。資格取得後すぐに独立する場合、23歳から27歳で独立開業することとなります。
公認会計士で独立している人の割合
厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」でみると、自営・フリーランスである公認会計士の割合は23.4%です。公認会計士の72.3% が組織に所属する職員・従業員となっています。
公認会計士が事務所を独立開業する場合、事務所のスタイルは主に次の3つといわれています。
税務業務中心の事務所
公認会計士が独立して事務所を開設する場合、税務業務を主とする会計事務所となることが多いといわれています。主な理由は次の3つです。
- 公認会計士は登録のみで税理士として活動できる
- 税務業務を主とすることで、企業数が多い中堅中小企業を顧問先として獲得しやくなる
- 地方は大企業が少なく、監査業務を求める顧問先は限られる
監査業務中心の事務所
企業や学校法人などと直接契約し、会計監査や内部統制の支援を中心とするスタイルです。
またフリーランスの公認会計士となって、監査法人の非常勤として働く場合もあります。
コンサルティング中心の事務所
監査スキルを活かして、会計、IPO、M&Aなどのコンサルティング業務を主とするスタイルです。
公認会計士が資格を取得後いきなり独立するメリットデメリット

公認会計士が資格取得後すぐに独立する場合の主なメリットとデメリットは次のとおりです。
公認会計士がいきなり独立するメリット
主なメリットは次のとおりです。
- すぐにやりたい仕事に集中できる
- 成功すると収入が大きく増える可能性がある
- ワーク・ライフ・バランスをとりやすい
公認会計士がいきなり独立するデメリット
公認会計士がいきなり独立開業する場合の主なデメリットは次のとおりです。
- 顧問先を獲得できず、収入が増えない可能性がある
- 税務業務に不慣れな場合、顧問先に迷惑をかける可能性がある
- 経験がない業務やわからないことを聞ける相談相手がいない
いきなり独立に向いている公認会計士の特徴
公認会計士として、いきなり独立することに向いている人の特徴は次のとおりです。
- 営業力がある
自ら顧問先を開拓できる営業力がある人です。
- 人脈がある
顧問先を紹介してもらえる経営者や、わからないことを聞ける同業者などの人脈をもっている人です。 - 努力家である
実務をおこないながら最新の会計知識や税制改正にキャッチアップするなど、高い学習意欲をもち続けられる人です。 - 独立心が強い
自ら事務所を立ち上げ、顧客を開拓し、自分のペースで業務をおこないたいと考える人です。 - バックグラウンドがある
親族が税理士事務所や事業を経営している、後継者不在の事務所を承継する見通しがある人などです。
公認会計士がいきなり独立するための事前準備

税務業務は監査と異なる部分があり、税務に戸惑わないよう独立開業前に次の準備をしておくことがおすすめです。
税務を学んでおく
税務の実務を経験しておくことがあげられます。監査法人在籍時から税務にかかわっておく、独立前に税理士事務所に勤務しておくなどです。
いきなり独立する場合、税務を勉強しつつ実務をおこなうこととなります。また不慣れな状態で税務をすすめると、提出書面の作成に戸惑うなど実務が滞る可能性があります。
事務所の特性を考えておく
独立開業後は、顧問先に数多くの同業事務所の中から自事務所を選んでもらうための“差別化”が重要となります。
金融庁のレポートによると、公認会計士が所属する中小規模監査事務所数は2,373事務所(2023年3月末)です。一方、税理士事務所数はその約10倍を超える28,244事務所があります。
顧問先から選ばれるためには、税務・会計業務に独自の強みをもつ、多様化する顧問先のニーズに対応できる事務所となるなど“差別化”が求められます。
【参考】2021年(令和3年)経済センサス-活動調査|e-Stat表番号7-1『72D税理士事務所』
人脈を作っておく
幅広い人脈を作っておきましょう。ここでいう“人脈”とは、大きくわけると次の3つの人脈のことです。
- 顧問先を紹介してもらえる人脈
- 実務を相談ができる、自らの参考となる先輩事務所経営者などの同業者
- 顧問先支援において協働できる士業、専門支援機関
所得税・消費税・相続税・資産税の実務を学んでおく
税務業務が多い所得税、過誤が多い消費税、難しいといわれる相続税・資産税について学んでおくのがおすすめです。
公認会計士がいきなり独立するときは税理士事務所勤務後がおすすめ

公認会計士がいきなり独立することは可能です。しかし独立開業後の円滑な成長のためには、税理士事務所に勤務し経験を積むことがおすすめです。税理士事務所勤務を経てから独立開業する主なメリットは次のとおりです。
- 税務の基本スタンスに慣れることができる
税務においては「重要性の基準値」がなく、税法に基づいて、円単位で丁寧に処理することが基本です。会計の考え方との違いに慣れておきましょう。 - 税務実務を身につけることができる
提出書面の作成など実務を経験することで、独立後の業務が円滑となります。 - 同業税理士など人脈が広がる
業務で困ったときに相談できる同業者の存在は、心強い味方となります。税理士会などに積極的に参加しましょう。
また経営革新等支援機関推進協議会など多くの税理士が加入する団体に参加することもおすすめです。全国各地で成長する事務所経営者のノウハウなどを参考とすることができます。 - 顧問先に対する幅広い支援スキルを磨くことができる
税理士は、顧問先の経営者から販路開拓、労務管理、IT化などさまざまな分野の相談を受けます。企業経営全体を俯瞰し、適切な支援をおこなう経験を積むことができます。 - 顧問先における経理処理に慣れることができる
顧問先の内部でおこなう経理を知っておくことで、証憑依頼や回収に慣れることができます。
また顧問先の経理事務を知ることで、バックオフィス業務の効率化を提案できる可能性が高まるなどメリットがあります。 - 中小企業支援策の活用法を身につけることができる
中堅中小企業向けの公的な支援策を上手に活用するスキルを身につけることができます。
補助金などの公的支援策は、経営者の支援ニーズが強い分野です。しかし、補助金、助成金、税制優遇制度などは種類が多い、独自の支援策を設けている地方公共団体がある、補助金などで採択されるためのテクニックが必要となるなど、ノウハウが求められます。
## 公認会計士が税務は経営革新等支援機関推進協議会がサポート
公認会計士は資格取得後にいきなり独立することが可能です。しかし独立後は税務業務が中心となることが多く、税務に不慣れであると顧問先の獲得がすすまない状況となる可能性があります。税理士事務所で経験を積んでから独立することで、独立開業の成功確率をあげることができるでしょう。
監査法人からいきなり独立したいと考える人、事務所の収益向上や同業事務所との差別化をお考えの事務所経営者様は、経営革新等支援機関推進協議会をご活用ください。
経営革新等支援機関推進協議会は、中小企業経営者から選ばれる事務所となるための各種サポートを月額30,000円(税別)で利用できます。
- 中小企業経営者がわかりやすい財務分析・提案ツール『F+prus』(エフプラス)
- 座学から実務までを学べる税理士事務所の監査担当者向け動画研修プログラム『ACADEMY』
- 事務所名を入れるだけ!すぐに活用できる販促ツールの提供
全国約1,700事務所が参加する経営革新等支援機関推進協議会へお気軽にご相談ください。